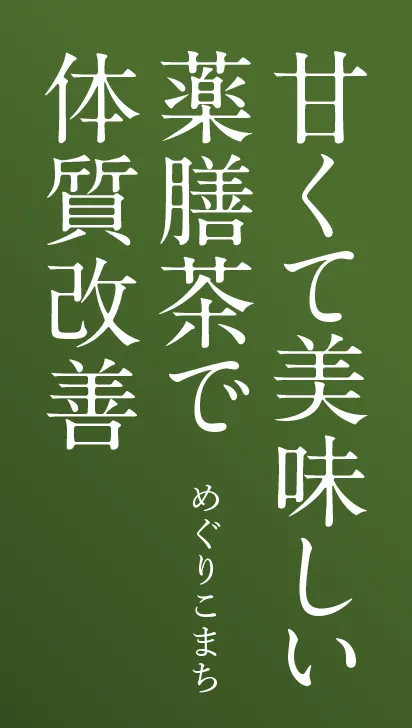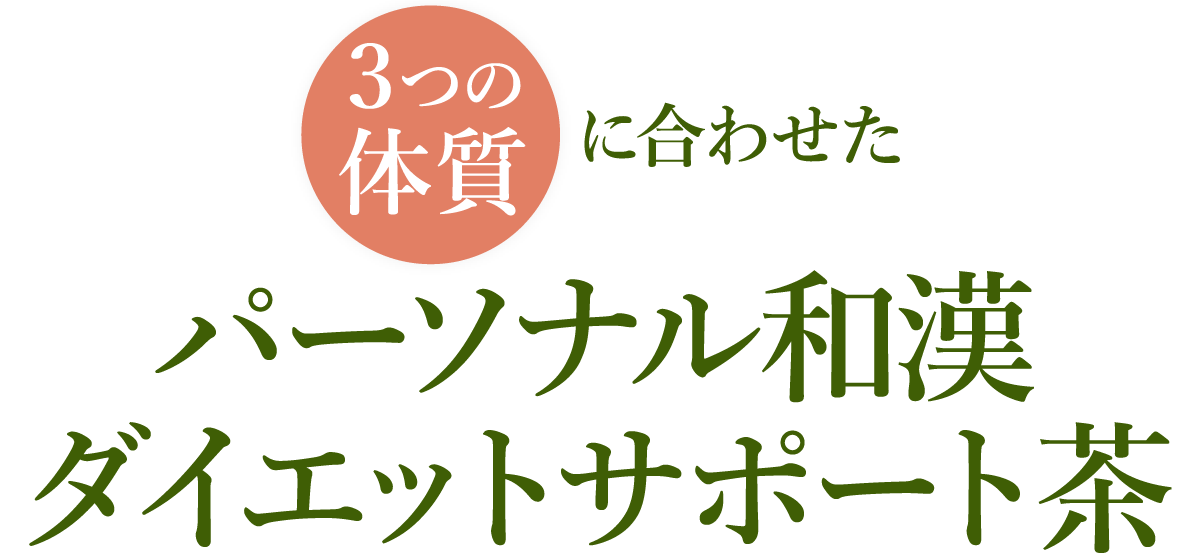病気予防やダイエットなど、薬膳茶に期待できる効果は、使用する食材によって異なります。自身の目的や体質に合った食材を取り入れることが大切です。
中医学の基礎知識を使えば、自宅でも簡単に薬膳茶が作れますよ。専門店の商品も活用して、無理のない薬膳茶習慣をはじめましょう。
目次
薬膳茶とは

薬膳茶とは、以下の2つの特徴を持つお茶です。
- 中医学の知識で体を整えるお茶
- 体質や目的に合った食材を組み合わせる
- 薬膳茶の効能は多種多様
薬膳茶で効果を得るには、基礎知識を確認して正しく生活へ取り入れることが重要です。体質や目的に合った食材を組み合わせれば、より高い効果が期待できるでしょう。
中医学の知識で体を整えるお茶
薬膳茶は、中医学の知識を使って体を整えるお茶です。中医学とは、2,000年以上前から人々の健康管理に利用されてきた中国伝統の医学です。「口にするものはみな、薬同様の効果を持つ」という薬食同源の考えに基づき、食材を活用して健康や美容を目指します。
中医学では、気(エネルギー)・血(栄養)・水(代謝)がバランスよく体内を巡っている状態が健康とされます。
また、薬膳茶で効果を得るには、陰陽のバランスも重要です。陰は「暗い」「寒い」、陽は「明るい」「温かい」などの要素を指し、体内で平衡を保っている状態が理想形です。
薬やサプリメントのような即効性はないものの、毎日飲み続けることでバランスが整い、体質改善を期待できるのが薬膳茶です。
体質や目的に合った食材を組み合わせる
薬膳茶は、体質や目的に合った食材を組み合わせて作ります。効果を高めたり抑えたりするために、2〜3個の食材をブレンドしましょう。
体質は気血水の巡りによって、気虚・血虚・陰虚・気滞・瘀血・痰湿の6つに分類されます。健康や美容のために補うべき要素は、体質によって異なります。まずは自身の体質を的確に把握することが重要です。
また、目的に合った効能を持つ食材を選んでください。中医学では、食材を酸・苦・甘・辛・鹹の五味で表します。五味は味や香りによる分類だけではなく、体にもたらす作用でも分けられます。例えば、酸味のある食材は肝臓のはたらきを促進し、消化を助けます。
理想の体になるには、食材の特性を確認し、体質や目的に合った要素を選ぶことが大切です。
薬膳茶の効能は多種多様
薬膳茶がもたらしてくれる効果は多種多様です。なぜなら、薬膳茶は一人ひとりの体調や体質、症状に合わせて作られているからです。
薬膳茶に使われている材料によって期待できる効果は少しずつ異なります。
例えば、水分を溜め込みやすい体質で、常に体がむくんでいる人には、代謝の働きをサポートする効能がある素材を用いたお茶と相性が良いのでおすすめです。
虚弱体質で活力が足りないと感じている人には、消化器官や腎臓の働きを整える効能がある材料が入っている薬膳茶を飲んでみましょう。きっとハツラツとした毎日が送れるはずです。
このように、薬膳茶は自分の体質や体調に合ったものを取り入れられるので、毎日の健康サポートに役立ちます。体の不調を改善したい人や、薬に頼らず自然の力で体を整えたいという方は、ぜひ薬膳茶を生活に取り入れてみてください。

薬膳茶に使用される主な食材8選

効果や効能の違いは、使われている食材によって異なります。
ここでは、薬膳茶に使われる主な食材を8つ紹介します。食材が持つパワーや、薬膳茶として摂取した時に期待できる効果も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
生姜
生姜には、辛み成分であるギンゲロール(ジンゲロール)が豊富に含まれています。ギンゲロール(ジンゲロール)には血行促進の効果が期待できるため、体の冷えにお悩みの人におすすめしたい食材です。
血行が良くなると、代謝アップも期待できるため、ダイエット中にもおすすめの食材です。
さらに、抗炎症作用や鎮痛作用もあるため、風邪の引き始めに生姜入りの薬膳茶を飲むと、症状の悪化を防止してくれるでしょう。
その他には、食物繊維やビタミンCなどを含んでおり、殺菌作用や免疫力向上にも役立つと言われています。
黒豆
黒豆は栄養が豊富に含まれているため、薬膳茶にもよく使われる定番食材です。黒豆には、強い抗酸化作用があります。そのため、近年アンチエイジング食材として注目されており、女性からの人気が高まっています。
さらに、食物繊維が豊富に含まれており、血糖値の急上昇を抑制をサポートしてくれます。ダイエット中の人にもおすすめですよ。
黒豆を薬膳茶に加えると、香ばしい香りが鼻いっぱいに広がり、リラックス効果も期待できますよ。
ゴボウ
私たちの生活に馴染み深い食材であるゴボウは、薬膳茶にもよく使われています。
ゴボウには食物繊維が豊富に含まれており、なかでも「イヌリン」という成分がたっぷり含まれています。「イヌリン」とは食物繊維の一種です。イヌリンは腸内の善玉菌を増やしてくれる効果があるため、便秘にお悩みの人におすすめです。
さらに、ゴボウにはポリフェノールの一種である「サポニン」も含まれています。「サポニン」には、血行促進や脂質吸収の抑制に効果が期待できるため、外食が多い人やダイエット中の人におすすめです。
ゴボウ茶が持つダイエット効果についてもっと知りたい人は、下記記事を参照してください。
ハトムギ
ハトムギは、生薬「ヨクイニン」の原料として使われています。この「ヨクイニン」には、痛みやしびれを和らげてくれる効果が期待でき、関節痛やリウマチに悩んでいる人が飲む漢方薬に配合されています。
さらに、ハトムギはたんぱく質が豊富に含まれているのが特徴です。その含有量は、なんと精米の2倍以上です。
栄養価の高さから薬膳茶にもよく用いられており、鎮静効果の他、デトックス効果、美肌のサポート、生活習慣の予防にも効果を発揮してくれます。
味わいのクセも少ないので、取り入れやすい食材でもあります。
ドクダミ
ドクダミには、カリウムやカルシウム、マグネシウム、鉄分などのミネラルが豊富に含まれています。特に、カリウムには利尿作用があるため、むくみやすい人や体内をデトックスしたい人におすすめです。
さらに、ドクダミには、クエルシトリン、イソクエルシトリン、ルチンも豊富に含まれています。特にルチンには動脈硬化を防ぐ働きがあるため、高血圧予防や生活習慣病予防にも役立ちます。
また、ドクダミには抗酸化作用を持つフラボノイドも含まれています。フラボノイドは、美肌サポートに役立つため、女性におすすめしたい食材です。
「ドクダミ」と聞くと、苦い、まずいイメージを、抱く人も多いかと思います。
確かに、生のドクダミは特有の苦味がありますが、乾燥してしっかり焙煎することで飲みやすい味わいに変化するので安心してください。ドクダミを薬膳茶としていただく際も、乾燥または焙煎をしているケースがほとんどです。
あずき
和菓子の材料に欠かせないあずきにはミネラルの一種である「カリウム」が豊富に含まれています。「カリウム」は体内の余分な塩分を排出してくれます。そのため、偏った食生活などで塩分が多い生活を送っている人や、塩分過剰によるむくみ対策におすすめです。
さらに、あずきには利尿作用がある「サポニン」も豊富に含まれています。「サポニン」はデトックス効果が高く、体内に溜まった余分な水分や老廃物の排出をサポートしてくれます。
また、あずきには強い抗酸化作用を持つポリフェノールも含まれているため、美肌のサポートにもおすすめの食材です。皮膚のターンオーバーを促してくれるビタミンB2、整腸作用のある食物繊維も含まれており、体の内側と外側の両方から美肌をサポートしてくれますよ。
あずきが入っている薬膳茶には上記のような効果が期待できることから、近年ダイエット食材として注目されています。
あずきが入った薬膳茶のダイエット効果をもっと知りたい人は、こちらの記事を参考にしてください。
なつめ
なつめとは、中国原産の植物のことです。形は楕円形で、赤くコロンとしたフォルムが特徴的です。生のなつめは甘酸っぱい味ですが、乾燥させるとギュッと甘みが凝縮されます。
食べやすい味わいである上、栄養価が高いスーパーフードです。そのため、薬膳茶にもよく用いられています。
その他、薬膳料理や、漢方薬としても使用されることも多く、中国はもちろん、日本でもメジャーになりつつある食材です。
なつめには、ビタミンB群、カリウムや鉄分などのミネラル、食物繊維などが豊富に含まれています。特にビタミンの一種である葉酸は、妊娠中の女性に欠かせない栄養素です。
葉酸には、胎児に欠かせない母乳の分泌を促進してくれる効果が期待できるため、妊娠中の女性や妊活をしている人は、ぜひなつめ入りの薬膳茶を日常生活に取り入れてみてください。
クコの実
杏仁豆腐や中華粥のトッピングとしてお馴染みのクコの実は、薬膳の材料としてメジャーな食材です。薬膳茶の材料としてもよく使われており、クセのない味わいが特徴です。
クコの実には高い抗酸化作用があります。特に「クコ多糖類(LBP)」には高いアンチエイジング効果が期待できます。老化防止はもちろん、生活習慣病や免疫力の強化にもおすすめです。
さらに、クコの実には「ベタイン」という成分が含まれています。「ベタイン」とは、アミノ酸の一種で、血圧を下げるサポートをしてくれる成分です。
ベタインは、動脈硬化のリスクを高める「血中ホモシステイン」を低減させる効果が期待でき、毎日の健康維持に役立ちます。
このように、薬膳茶に使われる食材は、生薬に使われる食材から私たちに身近な食材までさまざまです。高い健康効果が期待できる食材を掛け合わせてできる薬膳茶は、まさに現代人の健康維持に欠かせない飲み物と言って良いでしょう。
薬膳茶に期待できる効果

薬膳茶に期待できる効果は、以下の7つです。
- 病気を予防する
- エイジングケアできる
- 疲れを癒す
- ストレスを和らげる
- 体を温める
- 消化を助ける
- ダイエットをサポートする
体質に合った薬膳茶を飲み続ければ、さまざまな効果が期待できます。目的に合わせて食材を選び、無理なく健康や美容を目指しましょう。
病気を予防する
薬膳茶には、病気を予防する効果が期待できます。免疫を向上させる成分を摂取することで、健康な体を手に入れられるでしょう。
薬膳で免疫を補う食材といえば、なつめが代表的です。なつめは「一日3個食べれば老いない」といわれるほど栄養が豊富で、中国では果実を丸ごとかじって食べる習慣もあります。
また、高麗人参も免疫力の強化をサポートする薬膳です。自律神経の乱れを整えたり、免疫細胞にはたらきかけたりして、体を強くするといわれています。
高麗人参の独特な香りが苦手な方もいますが、健康作りには効果的食材なので、薬膳習慣に慣れてきた際には一度試してくださいね。
エイジングケアできる
飲むことで、エイジングケアができる点も薬膳茶のメリットです。抗酸化作用のある食材を使った薬膳茶は、年齢による肌や臓器の衰えを挽回してくれます。
抗酸化作用のある食材には、黒豆や桂皮があります。アントシアニンが豊富な黒豆には、アンチエイジングの効果が期待されます。炒った黒豆の薬膳茶は、香ばしい味わいが美味しくて人気です。
桂皮はシナモンで馴染みがあります。手足を温める作用もあるため、お茶にして朝飲むのがおすすめです。
エイジングケアは継続が大切です。飲みやすい味わいの薬膳茶を見つけて、習慣的に飲むようにしましょう。
疲れを癒す
疲れを癒してくれる薬膳茶があります。温かいお茶でほっと一息つくついでに、食材の持つ効能で体の疲れも取ってくれますよ。
干ししいたけはビタミンBが豊富で、疲労回復が期待できます。料理でよく使われる干ししいたけですが、市販の薬膳茶にも含まれていることが多い食材です。
また、疲れ目には菊花が効果的です。菊花は眼精疲労だけでなく、ドライアイや充血など目のトラブル解消が期待されます。薬膳茶にするには、乾燥させた菊花が使いやすくておすすめです。
健康を維持するために、仕事や家事の疲れはその日のうちに癒しましょう。夜寝る前の薬膳茶を習慣にすると、翌朝すっきり目覚められますよ。
ストレスを和らげる
薬膳茶には、ストレスを和らげる効果が期待できます。気の巡りを良くする薬膳食材には、イライラを落ち着かせたり、気持ちを前向きにしたりする作用があります。
ストレス緩和を目的とする場合、香りが良い食材を選ぶことがおすすめです。マイカイカやジャスミンなど華やかな香りを放つ花や、さわやかな柑橘系をお茶にして飲むと気持ちが落ち着きます。さらに、甘みをプラスすることで、緊張が和らぐ効果も期待できますよ。
食材の香りは、熱を加えすぎると飛んでしまう可能性があるため、抽出時間に注意してください。
ストレスは臓器のはたらきも弱めてしまう恐れがあります。心だけでなく、体の健康のためにも薬膳茶でリラックスする習慣を付けましょう。
体を温める
薬膳茶には、体を温める効果が期待されます。血流改善や保温効果を持つ食材を使用することで、冷え対策になる薬膳茶を作れますよ。
体を温める薬膳には、しょうがやしそがあります。生のしょうがやしそには、体の表面を温める効果があり、風邪に引きはじめで寒気を感じる際もおすすめです。乾燥させたしょうがは、体を内側から温める作用を持つため、冬の寒い時期には積極的に取り入れたい薬膳ですね。
冷えは臓器のはたらきを妨げてしまい、食欲不振や便秘などの症状にも繋がりかねません。日頃から体を温めることを意識して過ごしましょう。冷え対策の薬膳茶は、温~常温にして飲むと効果的です。
消化を助ける
消化を助ける薬膳茶があります。臓器のはたらきを促進させる薬膳は、消化不良や食欲不振などの症状を和らげますよ。
カルダモンは胃腸を温める食材です。温かい紅茶に2〜3粒入れると、胃もたれ緩和が期待できます。また、ゆずも消化器のはたらきを助ける食材です。すりおろした皮を薬膳茶に少量取り入れれば、食欲不振を改善できますよ。
胃腸が弱っていて食事が難しい場合でも、温かいお茶なら飲みやすいでしょう。食欲がないときは、体調に合った薬膳茶を栄養補給に活用してくださいね。
ダイエットをサポートする
薬膳茶はダイエットをサポートします。デトックス作用のある食材を使った薬膳茶には、むくみや代謝の改善効果が期待できます。
むくみが気になる方は、水の排泄を促進する成分を積極的に摂りましょう。薬膳茶でよく使用されるデトックス食材には、とうもろこしのひげや、はとむぎなどがあります。
薬膳茶で肥満の解消を目指す方には、あずきがおすすめです。なかでも、手軽なあずき茶なら生活にも取り入れやすく、脂肪燃焼によるダイエット効果も期待できます。

自宅でできる薬膳茶の作り方

自宅でできる薬膳茶は、以下の3つです。
- 心も体もすっきり「はとむぎ+マイカイカ」
- 体の中からポカポカ「しょうが+シナモン」
- 疲れた日には「なつめ+クランベリー」
はじめはスーパーで購入できる食材を使って、簡単にできる薬膳茶の作り方を試しましょう。薬膳茶で効果を得るには、飲み続けることが大切です。手軽なレシピで無理なく生活に取り入れてくださいね。
心も体もすっきり「はとむぎ+マイカイカ」
簡単にできる、はとむぎとマイカイカの薬膳茶は、心や体をすっきりさせたいときにおすすめです。
マイカイカは、バラのつぼみを乾燥させたもので、香りの良い薬膳です。デトックス作用を持つはとむぎに、マイカイカを組み合わせることで、リラックス効果もプラスされます。
はとむぎは手軽なティーバッグを使用しましょう。マイカイ花の花びらを入れたカップに、はとむぎ茶のティーバッグを添えて熱湯を注ぎます。蓋をして、2〜3分ほど蒸らしたら完成です。
マイカイカはがくを取り除いて、花びらのみ使用しましょう。また、時間に余裕のある際は、はとむぎ茶のティーバッグを煮出すと、より成分が抽出されて効果的ですよ。
はとむぎやマイカイカは人気な薬膳なので、スーパーでも購入できます。
体の中からポカポカ「しょうが+シナモン」
体の冷えが気になる方は、しょうがとシナモンの薬膳茶を試しましょう。しょうがは乾姜、シナモンは桂皮を使用するとより高い冷え緩和効果が期待できます。
作り方は乾姜と桂皮、好みのカフェインレスティーバッグを入れたカップにお湯を注いで、数分蒸らすだけです。
ボトルで作って持ち歩き、1日何回かに分けて飲むと冷え対策の効果がアップします。使用するティーバッグを変えて、好きな味わいを見つけましょう。
乾姜は体を芯から温める効能を持ち、桂皮には血流改善の作用があります。乾姜と桂皮の組み合わせは、体全体の冷え改善が期待できるため、生理痛に悩む方にもおすすめです。
疲れた日には「なつめ+クランベリー」
仕事や家事を頑張った日には、なつめとクランベリーを使った薬膳茶が疲労回復に効果的です。栄養豊富ななつめは、薬膳においてポピュラーな食材です。クランベリーは乾燥したもののほうが手に入りやすく、お茶にする際も使い勝手が良いでしょう。
作り方はまず、半分に割ったなつめと水を鍋に入れ、30分ほど煮出します。クランベリー入りのティーポットになつめも一緒に移し、3分蒸らしたら完成です。
なつめは滋養強壮のほか、エイジングケアや消化促進などをもたらす甘い果実です。ポリフェノールが豊富なクランベリーと合わせて、甘酸っぱい薬膳茶を楽しみましょう。
薬膳茶の効果を引き出すポイント

薬膳茶の効果を引き出すポイントは、以下の7つです。
- 食材は有機栽培や無農薬のものを選ぶ
- 旬の食材を取り入れる
- 食材の大きさを揃える
- 専門店の商品を参考にする
- 目的に合わせた比率で調合する
- 抽出時間に気をつける
- 劣化しないように保存する
健康や美容に対する効果を得るには、適切な薬膳茶を継続的に飲む必要があります。薬膳茶の作り方や食材選びのポイントを抑えて、理想の体を目指しましょう。
食材は有機栽培や無農薬のものを選ぶ
薬膳茶を作る際、食材はできるだけ有機栽培や無農薬のものを選びましょう。食品に農薬や化学肥料が残っていると、本来食材が持っている効能が弱まってしまう可能性があるので注意が必要です。
ただし、有機栽培や無農薬であっても、食材の鮮度が悪いと薬膳茶への効能や味に影響を及ぼしかねません。ですから、食材を購入したらできるだけ早く薬膳茶作りに取り掛かりましょう。
旬の食材を取り入れる
旬の食材を取り入れることで、薬膳茶の効果はより引き出せます。体の調子は気候や環境によって変化するため、薬膳を選ぶ際は季節に合った食材を選びましょう。
寒い時期に体を温めたい場合は、ゆずを使った薬膳茶を試してください。冬に旬を迎えるゆずは、血管を広げて手足の冷えを改善する効果があります。
また、暑い時期にも冷房で体が冷えてしまうことがあります。夏の冷えには、6月〜9月が旬のしそを使った薬膳茶がおすすめです。しそには、体が冷えすぎてしまうのを防ぐ効果と、夏バテによる食欲不振を緩和する作用が期待できますよ。
旬の食材は栄養価も高いため、健康維持のために積極的に取り入れましょう。
食材の大きさを揃える
薬膳茶の効果を引き出すには、使用する食材の大きさを揃えることがコツです。同じ時間でバランス良く成分を抽出できるように、均等なサイズ感を考慮しましょう。
薬膳茶を作る際は、食材が入ったカップに熱湯を注ぎ、しばらく蒸らして成分を抽出させます。抽出が足りなかったり、雑味が出てしまったりするのを防ぐために、食材は大きさを揃えてカットしてくださいね。
豆や穀物類は切り分けられないため、他の食材のほうでサイズを調整するのが得策です。
また、花や柑橘類など、熱を加え過ぎると香りが飛んでしまう食材もあります。香りを楽しみたい食材は先に取り出してしまうのも、美味しい薬膳茶を作るポイントの一つです。
専門店の商品を参考にする
専門店の商品を参考にすると、健康や美容に効果的な薬膳茶を作れます。薬膳茶専門店の商品は、プロによって適切な食材が調合されています。専門家の調合を参考にすることで、自宅で作る際も失敗のない食材選択ができますよ。
市販の薬膳茶のパッケージには、「血流改善」「デトックス」など期待される効果が記載されています。気になる商品の成分表をみて、含まれる食材をまねすれば、自宅でも同じような味わいや効能の薬膳茶が作れるでしょう。
「めぐりこまち」のように、無料で体質診断サービスを行っているお店もあります。自身の体質に合った商品を見つけられると、参考にしやすいですね。
専門店の気になる商品は一度飲んでみて、飲みやすさや効果を確認しましょう。
目的に合わせた比率で調合する
薬膳茶の効能をしっかり感じたい場合は、目的にあった比率で食材を調合するのもポイントです。
例えば、冷え性の改善を目的としている場合は生姜の比率を増やし、アンチエイジングを目的としている場合はクコの実の比率を増やしてあげましょう。
ただし、目的ばかり気にして食材の相性を無視してしまうと、飲みづらい味わいになってしまう可能性があるため注意が必要です。まずは相性の良い食材を2〜3種類ブレンドしてみることから始めてみてください。
抽出時間に気をつける
薬膳茶の抽出時間は長すぎても短すぎてもいけません。抽出時間が短すぎると、食材が持つ栄養成分が十分に抽出されず、反対に長すぎると成分が変質してしまう恐れがあります。
抽出時間は食材の種類や、食材の大きさによって異なるため、食材に合った抽出時間を守るのがポイントです。
また、抽出時間だけではなく、抽出温度も重要なポイントです。温度が低いと栄養成分の抽出に時間がかかり、反対に温度が高いと成分が変質する恐れがあるため、時間と共に温度も正確に測りましょう。
劣化しないように保存する
薬膳茶の成分は劣化しやすいため、適切な環境で保存することも重要なポイントです。薬膳茶は、光や熱、湿気に弱いため、光を通さない容器に密閉し、直射日光の当たらない冷暗所で保存してください。
また、空気に触れると酸化し、栄養成分が変質する可能性があります。そのため、密閉容器に入れて空気にできるだけ触れないようにしましょう。
しかし、いくら保存方法に気を配っていても、時間の経過とともに少しずつ劣化していきます。長期保存は避けて、1週間程度で使い切りましょう。
以上のことから、薬膳茶の保存におすすめなのは金属容器です。もし使い切った茶筒があれば、薬膳茶の保管に役立ちますよ。
「めぐりこまち」の薬膳茶ならその人に合った効果が期待できる

薬膳茶を自分で作る場合、食材を自分で調合したり、抽出温度や抽出時間に気を配ったりと手間と時間がかかります。そこでおすすめしたいのが「めぐりこまち」の薬膳茶です。
「めぐりこまち」の薬膳茶は最初から体質別にカスタマイズされているので、目的に合った薬膳茶がすぐにいただけます。ここからは、めぐりこまちについて詳しく紹介します。
展開されているのは3種類
めぐりこまちは全部で3種類展開されています。
「青のめぐりこまち」はむくみやすい体質の人に作られており、高いデトックス効果が期待できる薬膳茶です。
「白のめぐりこまち」はエネルギー不足を感じている人のために作られており、代謝を高めイキイキとした毎日をサポートしてくれます。
「黄のめぐりこまち」はストレスを感じやすい人のために作られており、高いリラックス効果が期待できます。
自分の体質や目的が分からない人のためにLINEで体質診断も実施しています。ぜひこの機会にめぐりこまちを取り入れてみてくださいね。
さまざまな食材がバランス良くブレンドされている
めぐりこまちの薬膳茶は、世界中から厳選した15種類の茶葉を体質に合わせてバランス良くブレンドされています。
世界中から集まった茶葉は日本の工場で厳重に管理されているため、品質も保証されています。
飲みやすい味わいなので薬膳茶が初めての人も安心
めぐりこまちはほんのり甘い味わいなのが特徴です。そのため、薬膳茶初心者の人も美味しくいただけます。
薬膳茶にはさまざまな健康効果が期待できますが、苦い味わいですと毎日続けるのは困難です。
その点、めぐりこまちは全種類味わいにこだわって作られています。ぜひお試しください。
医師監修なので高い品質が保証されている
めぐりこまちは高卓士医師監修の薬膳茶です。そのため、品質の高さが保証されています。
めぐりこまちは飲みやすさや高い効能からリピーターが多い薬膳茶です。毎日の習慣にして健やかな毎日を過ごしましょう。
購入後のアフターサポートも充実
めぐりこまちは商品が届いた後のアフターサポートも充実しています。
購入した後、薬膳学、栄養学、医学的知識に優れた専属アドバイザーが健康状態をチェックしてくれます。この機会に薬膳茶に関する質問や体のお悩みをぜひ相談してみてくださいね。
薬膳茶を取り入れる際の注意点5つ

最後に、薬膳茶を取り入れる際の注意点を5つ紹介します。
注意点を意識して、薬膳茶を正しく安全に取り入れましょう。
服薬中や通院中の人はかかりつけ医に相談する
薬膳茶は漢方にも使われている生薬が用いられています。そのため、服薬中や通院中の人はかかりつけ医に相談しておきましょう。
妊娠中や授乳中の人も事前に相談しておくと安心です。万が一、体調に異変を感じた場合は飲むのをやめて、すぐに医療機関を受診してください。
カフェインの摂りすぎに気をつける
薬膳茶にはカフェインが多く含まれている場合があります。カフェインの摂りすぎは下痢や吐き気など、体調を崩す可能性があるため、1日に飲む量を決めておきましょう。
体調によっては逆効果になる可能性がある
薬膳茶は毎日の習慣として飲むことをおすすめしていますが、体調が悪い時に飲むと返って具合が悪化する可能性があるため、注意が必要です。
体調が悪い日は一旦飲むのをやめて、体調が戻り次第再開することをおすすめします。
材料の特徴をよく理解する
薬膳茶の特徴をよく理解しておくことも重要です。
特に、材料が持つ効能を理解すれば、自分の体質に合うかどうかも判断できるようになります。ですから、薬膳茶に何が入っているか分からないまま飲み続けるのは避けましょう。
一気飲みは避ける
薬膳茶の一気飲みはおすすめできません。なぜなら、一気飲みをすると逆にむくみやすくなってしまうからです。
薬膳茶は一気飲みではなく、少量をこまめに飲むのがおすすめです。たとえ、効能を得たいからといって短時間でたくさんの量を摂取しないようにしましょう。

薬膳茶の効果で体のバランスを整えよう

薬膳茶には、病気予防やダイエットなど多くの効果が期待できます。気血水や陰陽など、中医学の基礎知識を使って食材を選べば、自宅でも手軽に薬膳茶を楽しめますよ。
はじめての方は簡単なレシピや専門店の薬膳茶から試して、無理のない健康習慣を目指しましょう。